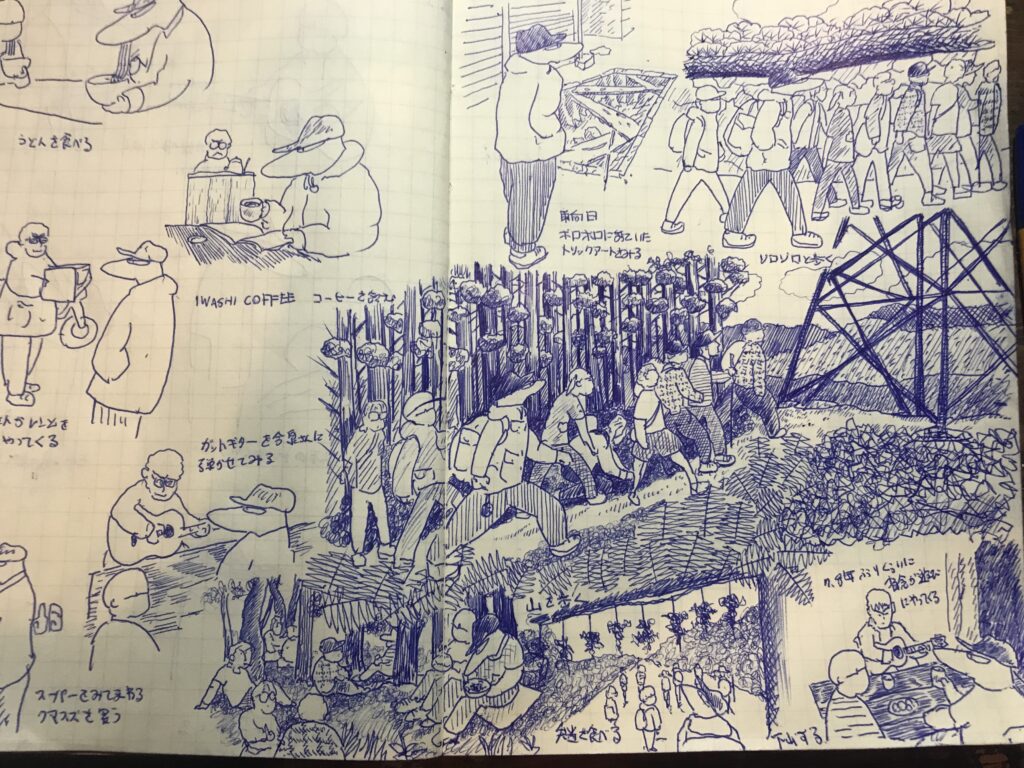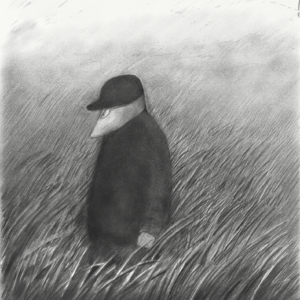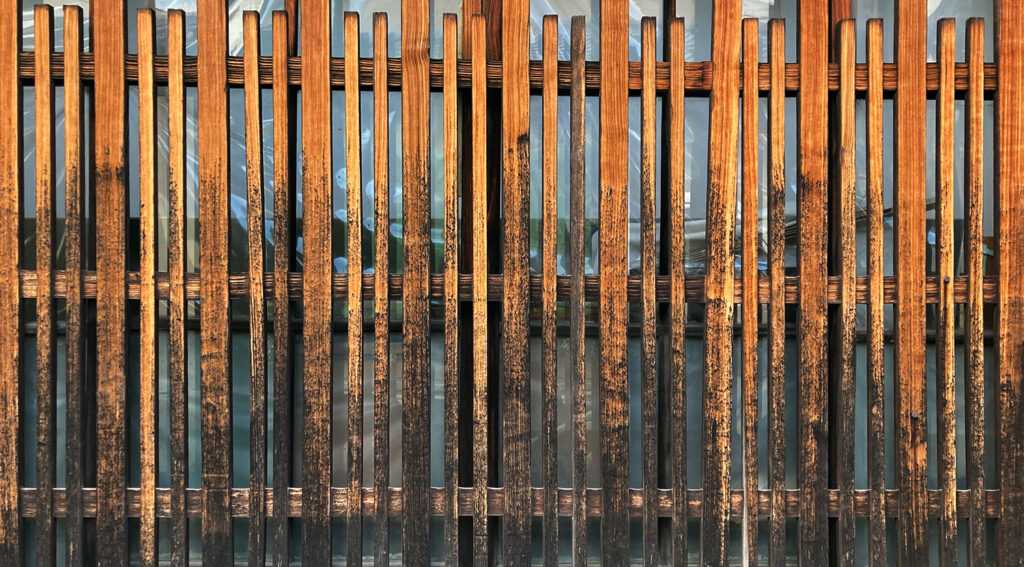同じオサノート投稿仲間の夫でも記載がありましたが、
3歳の娘の七五三をしました。
梅柄の着物に頭には梅の飾りをつけて、
娘が一番引き立つように家族はみんな白で統一した服装で。
北野天満宮を選んだのは、私の実家が福岡の太宰府天満宮近くで
かつて飛梅が行き交ったように、
二つの地域が結ばれているように感じたから。
紅葉真っ盛りの北野天満宮を、
スッポ脱げる草履をしょっちゅう履かせてやりながら
まさに飛んでいく梅のような娘が
いつかは京都からも福岡からも離れて、
どこか遠くの地で暮らすようになるかもしれないな….
と切なくなりました。
そういえば、最近読んだ教本『京のあたりまえ』(著者:岩上力/光村推古書院)に
西陣にある「一条戻り橋」は娘が嫁いだ先から戻ってくるから、
嫁入り時には渡らせない風習があると記載がありました。
人生いろいろ。
戻ってきたっていいんじゃない?
むしろ戻ってきたら嬉しいんだけどな。
娘のいない人生なんて、
考えられなくなったこの三年でした。
(最後の焼肉時には子供は寝てしまって、夫とゆっくり楽しくいただきました。)