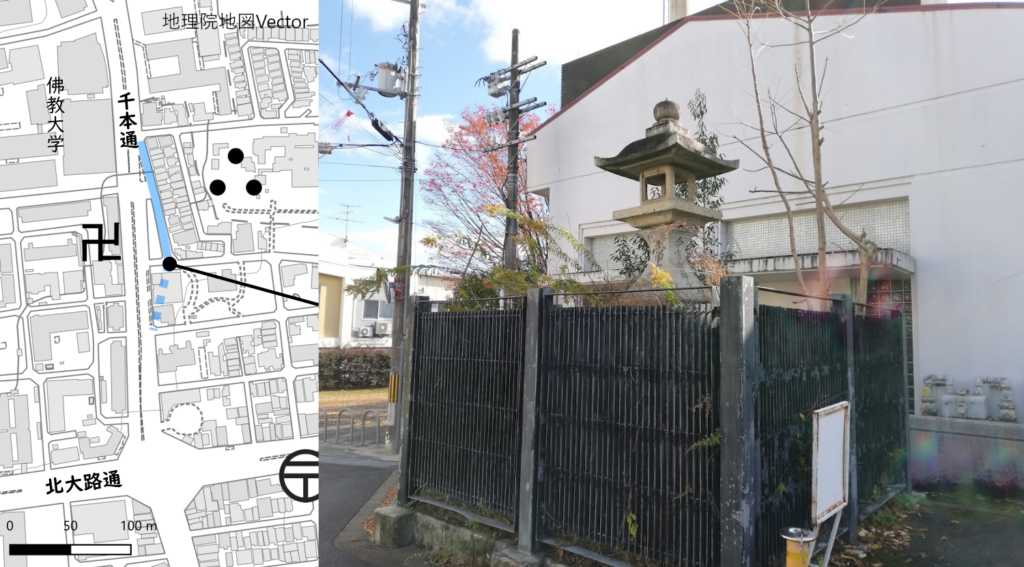現在、「北野寮」という建物の解体工事が進んでいる。北野天満宮の門前、御前通に面した場所に建つ、京都府警察の単身寮である。
子どもの頃から、天神さんにお参りに行くときはいつも北野寮の前を通っていた。昔はまったく気にも留めていなかったが、改めて見るとなかなか洒落ている。モダニズム建築に特徴的な水平に連続する窓の合間に、小豆色のパーツがリズム良く配置されている。各階の区切りは長押のようにも見え、カラーリングも相まって和の趣が感じられる。
この記事の執筆時点ではすでに建物のまわりに足場が組まれており、北野寮は間もなく解体されるだろう。特に文化財に指定されているわけでもなければ、マニアの間で話題になるような建築でも(おそらくは)ない。
しかし、どんな建物であれ、取り壊されると聞くととたんに名残惜しさがこみ上げてくる。それが小さい頃から目にしてきたものであればなおさらだ。この風景が失われたとき、私は何を感じるのだろうか。まったく語られてこなかったこの建物の最後の姿を、ここに留めておきたい。